建築基準法について解説してきた連載も今回が最終回となりました。
無秩序な開発を防ぐことを目的とした「集団規定」では(1)道路に関する制限、(2)用途制限、(3)建ぺい率、(4)容積率、(5)高さ制限、(6)低層住居専用地域内の制限、(7)防火・準防火地域内の制限、(8)敷地面積の最低限度について定めていますが、今回はそのうち後半部分の(5)~(8)について解説いたします。
現物の不動産投資を行う上で、このような規制に関する十分な調査は欠かせませんので、しっかりチェックしていきましょう。
(過去記事はこちら:第1回 単体規定 / 第2回 集団規定(1))
(5)高さ制限
周辺環境の保護のため、建築物の高さについて、以下のような制限があります。
<斜線制限>
斜線制限とは、周辺地域の採光や通風に支障を来さないように、建築物の各部分の高さを規制するものです。こちらで詳しく解説していますので、ご参照ください。
<日影規制>
日影規制とは、北側の敷地の日当たりを確保するための制限で、主に住居系の地域に適用されます。こちらで詳しく解説していますので、ご参照ください。
(6)低層住居専用地域内の制限
よりよい住環境を実現するため、第一種・第二種低層住居専用地域のみに適用される規制として、以下のものがあります。
<絶対高さの制限>
第一種・第二種低層住居専用地域内では、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画で定めた高さを超えて建築することはできません。ただし、以下の場合には、その高さを超えて建築することができます。
- ①周囲に広い公園等がある建築物で、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと特定行政庁が認めて許可したもの
- ②学校等、その用途によってやむを得ないと特定行政庁が認めて許可したもの
<外壁の後退距離の限度>
第一種・第二種低層住居専用地域内では、建築物の外壁から敷地境界線までの距離(=外壁の後退距離)は都市計画で定めた限度以上でなければなりません。
なお、外壁の後退距離は必ず定めなければならないものではなく、行政の判断で、必要があれば定められるものです。
都市計画で外壁の後退距離を定める場合は、その限度は1.5mまたは1mとされています。
(7)防火・準防火地域内の制限
火災の延焼等を防止するため、建築物が密集している地域を防火地域または準防火地域に指定し、建築物の構造に一定の制限を設けています。
なお、建築物が複数の地域にまたがる場合は、原則として建築物の全部に対して最も厳しい規定が適用されますが、防火壁により区画されている場合はその限りではありません。
<防火地域内の制限>
防火地域内では、原則として、以下の制限があります。
- ①地階を含む階数が3以上の建築物または延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物としなければなりません。
- ②上記以外の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。
ただし、次の建築物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物にしなくてもよいとされています。
- ①延べ面積が50㎡以下の平家建ての附属建築物で、外壁・軒裏が防火構造のもの
- ②高さが2mを超える門または塀で、不燃材料で造り、または覆われたもの
- ③高さが2m以下の門または塀
また、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔等で、以下のいずれかに該当するものは、その主要部分を不燃材料で造り、または覆わなければなりません。
- ①建築物の屋上に設けるもの
- ②高さが3mを超えるもの
<準防火地域内の制限>
準防火地域内では、以下の制限があります。
- ①地階を除く階数が4以上または延べ面積が1,500㎡を超える建築物は、耐火建築物としなければなりません。
- ②地階を除く階数が3以下で、延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。
- ③地階を除く階数が3で、延べ面積が500㎡以下の建築物は、耐火建築物、準耐火建築物または一定の防火上の基準に適合する建築物としなければなりません。
また、準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁・軒裏で延焼のおそれがある部分を防火構造としなければなりません。
<防火地域と準防火地域に共通する制限等>
防火地域と準防火地域に共通する制限等としては、以下のものがあります。
・屋根:一定の技術的基準に適合するものでなければなりません。
・外壁の開口部:延焼のおそれがある部分に、防火戸その他の防火設備を設けなければなり
ません。
・外壁:耐火構造のものは、民法の規定に関わらず、その外壁を隣地境界線に接して設ける
ことができます。
(8)敷地面積の最低限度
建築物の敷地面積は、都市計画で定められた敷地面積の最低限度以上でなければなりません。なお、都市計画において敷地面積の最低限度を定める場合は、その最低限度は200㎡を超えてはなりません。
これまで3回にわたって建築基準法についてみてきました。建築基準法は、建築物に関する最低基準を定めた基本的な法律であり、その建築物が建築基準法に適合しているかどうかは不動産投資にあたって重要なポイントになります。
不動産を選定される際にはぜひご参考になさってください。
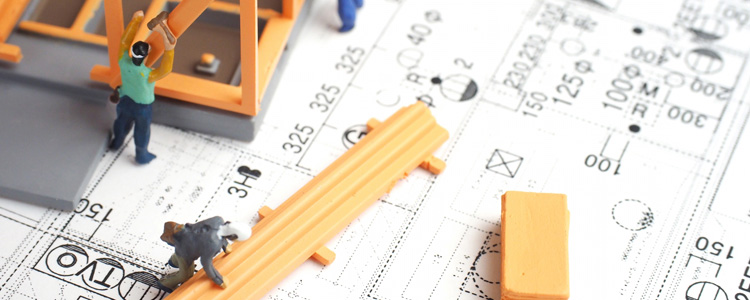
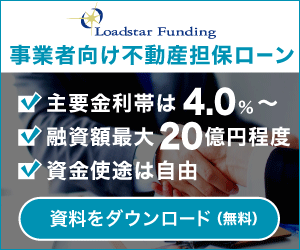

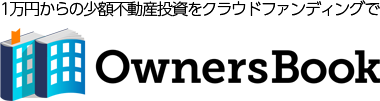
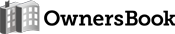
0 件